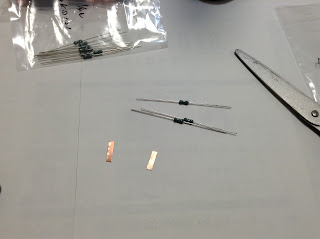プリアンプを作るにあたって、オペアンプに何を使うかです。
メインアンプの場合も、いくちかのパワーICを比較して、結局LM3886を選択したので同じような検討をしてみたい。
製作の参考にしようとしている、安井 章さんの場合は、2015年11月、2016年1月(いずれも無線と実験誌)では、イコライザアンプとして、OPA627AP、LT1363、OPA603、LT1226等が差し替えられて、微妙な差で評価がされています。
改めて、オペアンプの本を調べても、オーディオ用に絞った本はありません。
唯一無線と実験で河合 一さんが、2010年~2011年にかけて、合計20回の「自作派のためのオペアンプの正しい理解と使い方」というシリーズを書いておられます。
毎回6ページほどの記事が見つかり、現在すべてを読み直しています。
AD797、OPA604、5532/5534、OPA627、LM49860、MUSES8820、LME49726、OPA2353、LT1115、OPA2134、OPA1632、MAX4475、SSM2135、MAX4411などのオペアンプが紹介されています。
各オペアンプの特性比較や、特徴及びTEST DATA SHEETにある応用回路の紹介などが記載されて参考になりそうです。
メインアンプの場合も、いくちかのパワーICを比較して、結局LM3886を選択したので同じような検討をしてみたい。
製作の参考にしようとしている、安井 章さんの場合は、2015年11月、2016年1月(いずれも無線と実験誌)では、イコライザアンプとして、OPA627AP、LT1363、OPA603、LT1226等が差し替えられて、微妙な差で評価がされています。
改めて、オペアンプの本を調べても、オーディオ用に絞った本はありません。
唯一無線と実験で河合 一さんが、2010年~2011年にかけて、合計20回の「自作派のためのオペアンプの正しい理解と使い方」というシリーズを書いておられます。
毎回6ページほどの記事が見つかり、現在すべてを読み直しています。
AD797、OPA604、5532/5534、OPA627、LM49860、MUSES8820、LME49726、OPA2353、LT1115、OPA2134、OPA1632、MAX4475、SSM2135、MAX4411などのオペアンプが紹介されています。
各オペアンプの特性比較や、特徴及びTEST DATA SHEETにある応用回路の紹介などが記載されて参考になりそうです。